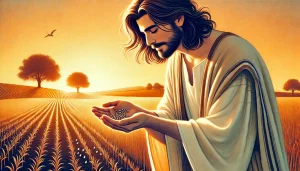私はマーケティングに関わる仕事を通算4年くらいしてきました。単純に、正解のない追求が面白かったのです。心理と技術と工夫と目利きで数字が変わってくるというか、動かしていく感覚がたまらなく好きでした。しかし最近、マーケティングって疲れるなぁと思ったのです。かつては好奇心いっぱいに学んでいた分野だったのに、いまは「気持ち悪い」とさえ感じてしまう。その違和感は、ほんの些細なことから始まりました。踊り、踊らされる偽りの虚構な世界について考察してみました。
マーケティングが面白いと思った時

かつての私は、ダイレクト出版さんから出ている情報を知ってから、マーケティングの面白みを実感しました。マーケティング思考で見る市場は、新しい視点を持てたので自分が博識というか、賢くなれた感覚すらありました。そして、コピーライティングが楽しくてたまりませんでした。
ダン・ケネディという世界的なコピーライターに関する書籍は、特に面白かったですね。ダン・ケネディの最大の強みであり、私が何よりも惹かれたのは「売上に直結する文章」を書くというテクニック。セールスレター、DM、広告、ニュースレター、講演──どれも“読者の感情と財布を動かす”よう設計されています。華麗でも文学的でもなく、「買わせる」「反応させる」ことに特化した実務的コピーライティング。「売れたかどうか」が評価基準という、シビアな世界で何十年も結果を出し続けてきた人物です。
この人を踏襲して売上を立てていくことが楽しかったのですが・・・いつしか私は疑問を持つようになりました。というのも、現実世界は、ダン・ケネディのようにはいかないから。
数字を追い続ける終わりなきゲーム

マーケティングは企画だけではもちろんありません。常に数字を分析していく必要があります。「CVRを上げるためには」「LTVを最大化するなら」「顧客の行動データを見て最適化を」――そんな言葉たちが当たり前のように飛び交う世界なのです。それに疲れ、いつしか私は心を失っていきました。
数字ばかり信じると、人は共感できなくなる
マーケティングの世界では、数字がすべてです。特にお金を稼ぐという意味では、よりシビア。お客さんが喜んでもらえたかとかは、究極のところどうでもいい。入金がなければ成功とはいえない。リストをとらなければ無駄足。どれだけ魅力的な想いを語っても、どれだけ人に寄り添ったサービスであっても、「数字で証明できなければ、意味がない」という空気があると個人的には思っています。
それはある意味、正しいのだと思います。企業活動としては、結果が必要です。再現性も必要です。しかし、だからといって、すべてを数字で測ろうとする世界って、あまりにも不自然ではないか? と私は思うようになりました。
何のためにマーケティングをしているのか
たとえば、「感動した」「この文章が心に響いた」と言ってもらえても、それは数値にしづらい。一方で、ただタイトルに“煽りワード”を入れて、クリックさせた記事の方が「成果」とされる。「届けたい思い」よりも「CVRが高い構成」が勝ち、「ユーザーの気持ち」よりも「直帰率の改善」が偉い。
インフルエンサーマーケティングなんかでは、フォロワー数だとか、再生数だとかで、凄いの何のと、数字そのものが価値になっているのです。なぜ、こんなにアホみたいな世界になってしまったのか。それが私の、正直な気持ちです。何かを忘れてはいないか・・・そう、信頼を。
私はこうして、うつ病になりました
これは大げさでも、比喩でもありません。マーケティングの仕事を通じて、私は本当に、心を病みました。日に日に気持ち悪さを感じたのです。「クリック率・開封率は?」「ベネフィットは?」「もっと具体的に書いて」このような言葉を浴びせられる日々の中で、「私が本当に届けたいもの」や「この商品が持つあたたかさ」が、無意味なものに思えてきたのです。なんというか、私自身が結構熱いタイプかつ、人に喜んでほしいという根っからのサービス心がどこかにあるのだと思います。与えたいという心が。
だからなのか、数字ばかりを追い、届ける先の人がどう喜ぶかという心の繊細な部分を訴求したところで、周りの人からは「それよりも〜」と何かが欠落したフィードバックと要求を受けました。いつからか、誰かの心を動かすために仕事をしているのではなく、数字を上向きにすることが目的になっていました。いかに反応させるか、クリックさせるか、と過度に。大事なことですが、本当に過度に。そんな仕事を続けていたら、当然ながら、心は悲鳴をあげます。
マーケティングの本質とは?
うつ病で休職をし、自分が今まで携わってきたマーケティングに対して熟考しました。少し私の思いを語らせてください。
そもそも、マーケティングは商品ありきですよね。その商品にもレベルがあります。お金儲けのためだけに用意したものなのか、想いあってのものなのか。後者には、必ず物語があります。しかし、今やマーケティングのほとんどは、物語をつくっています。ですから、前者のものも、付加価値のようにつくっています。しかし、つくった物語はつまらないです。本物の物語には真実味がり、それを人は微細に感じとります。私はそれを読み取っているつもりです。ですから、売れない商品・売れる商品は大体わかります。そういう目を仕事でも、もちろん生まれた環境を通しても磨かれてきました。
ともあれ、商品あってのマーケティングですが、現代はとにかく広告競争なわけで、そんなことはおきざりです。いかに反応させ、リストをとり、訴求し続けるかという、無理矢理感、押し売り感、必死感、馬車馬状態です。お客さんのことを本当に思うならば、これは良き商売とは必ずしも言えません。そして働く人にとっても、です。これらの違和感が気持ち悪くて仕方がありませんでした。
つまり、「人の温もりを忘れたマーケティングは、本質を見失う」というのが私なりの見解です。マーケティングは本来、人を理解するためのものだったと思います。冒頭で述べたダン・ケネディもテクニシャンではありますが、その始まりは人を理解してこそ、伝えたつもりではなく、伝わるものをつくるという根本があると思うのです。それが、今では人を“管理する”“操作する”道具になってしまっています。私は、自分が感じていた違和感はそういうところなのです。
これからの時代、必要なのは「数字と心のバランス」
誤解のないように言えば、私はマーケティング自体を否定したいわけではありません。数字も大事ですし、戦略的に考えることも必要です。生計を立てるのですから、賢く計画的に物事を進めるのも資本主義では当たり前でしょう。ですが、それがすべてになってしまったとき、人は簡単に壊れます。
本来、マーケティングとは「伝える」ための技術であり、「わかりあう」ための道具であるはずです。
誰かの心を動かすために使うからこそ、意味がある。私自身は今、「売るためにやるマーケティング」から、「伝えたい思いを形にするマーケティング」に戻っていきたいと思っています。そういうお仕事をしたいですね・・・。
違和感は、あなたの中の“人間らしさ”の証かもしれない
ここまで読んでくださった方に伝えたいのは、「違和感」は悪いものではないということです。むしろ、心がまだ生きているからこそ、感じられるもの。これはAIにはわかりません。心の微細さというのは、分析だけでは見えません。人間、そんな単純ではないですし、事細かな血の通った何かをふと感じた時に、すべてを理解することだってあります。恋愛と同じですよ。分析ばかりして、うまくいくと思いますか?むしろ、どんどんおかしくなります。理論的には合っているとか、そういうロボット的な話ではないのです。
数字や効率に支配されそうになったときこそ、「私は誰に、何を届けたいんだっけ?」そう問い直す勇気を、忘れずにいたいと思います。それこそが私の持ち味であり、大事にしたいところ。共感してくださる方がいれば嬉しいです。